4130満洲を故郷とする子どもたち
てらいんくの評論
満洲を故郷《ふるさと》とする子どもたち
石森延男の戦中・戦後満洲児童文学考
磯田一雄:著
四六判上製 496ページ
定価:3,800円+税
ISBN978-4-86261-192-5 C0095
発行:2025年3月
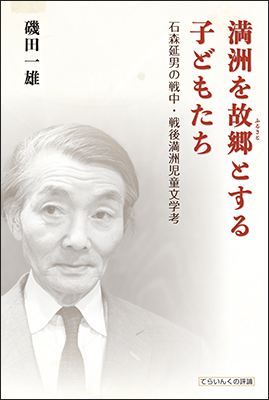
内容
満洲に生きた子どもたちにとっての「故郷」とは――。
それまで平板であった国語教材にドラマをもたらした文学者・石森延男。ファシズムの時代、満洲児童文学運動のカリスマ的リーダーでもあった彼が作品に盛り込もうとしたメッセージは何であったか。
戦中期の『咲きだす少年群』『日本に来て』『スンガリーの朝』、戦後の『わかれ道』『秋の日』『親子牛』など、満洲に関わる作品群を丹念に考察する評論集。つぶさに観察して描かれた子どもたちの姿や満洲の社会的・教育的背景等をもとに読み解いていく。
「はじめに」より
石森の児童文学や教科書教材の面白さとは何だったのだろうか。一口にいえば、そこには人間がいてドラマがあったということではないかと思われる。特に教科書教材は平板で、血の通った人間が出てこなかった。そこに人間のいるドラマのある文学作品を持ち込んだのが石森だったといえよう。筆者の子ども時代の体験とも重なるが、日本のファシズムが最高潮に達した時期に、彼が如何に児童文学において対応していたか、石森のいう(戦時下の)「三部作」を中心に、彼がそこに盛り込もうとしていたメッセージは何であったかを、まず読み解いてみたいと考える。
目次
はじめに 石森延男とわたし
1 満洲は「故郷」か
2 子どもの頃知った石森作品
3 石森延男の系譜
4 時代の証言としての石森作品
第Ⅰ部 『咲きだす少年群』――満洲・満洲国を超えて中国大陸へ
1 『咲きだす少年群』のあらすじ
2 『咲きだす少年群』の成立過程
3 「大陸に巨歩を印した」とは――この小説のねらい
4 子どもの生活に落とす大人の影
5 死の意味を考える――「お国のため」に命を捨てよ
6 戦時体制とアメリカ文化への憧れ
7 日本語による宣撫活動―啓二の人物像
8 洋の級友たち――モンゴル人・白系ロシア人の子を含めて
9 満人(中国人)の友だち・志泰
10 洋と啓二の出会い
11 大陸在住日本人批判
12 もう一つの日本人の弱さ――他民族に学べ
13 日本語という「愛情」と日中戦争という「体罰」
14 蒙古風とともに
15 各民族の子どもの位置
16 日中戦争の捉え方――戦後版はどう変わったか
第Ⅱ部 『日本に来て』――「日本のすばらしさ」を求めて
1 『日本に来て』のあらまし
2 なぜ小説でなく童話なのか
3 日本に戻るわけ
前篇 大連から神戸までの船旅で二郎が出会ったこと
(1) 船中で出会った絵かきさん
(2) 上海まで父を探しに行ったチョンイの話
(3) 二郎の反省――誇れるものが自分にあるか
(4) 初めて見る日本――カルチャー・ショック
(5)アメリカ人父子の話を聞いて
後篇 日本に着いてから
(6) 神戸から東京へ――日本の「すばらしさ」を発見する
(7) 『日本に来て』のねらい
第Ⅲ部 『スンガリーの朝』――白系ロシア人との出会い
1 この作品の概要と特徴
2 東京を発つ――家庭事情で満洲のハルビンへ
3 船中で聴くラジオ
4 爾霊山を訪ねる
5 特急「あじあ号」に乗る
6 ハルビンに着いて
7 ハルビンの学校
8 白系ロシア人への接近
9 難民(エミグラント)白系ロシア人
10 キリスト教への関心――初出版と改訂版の違い
11 日本人であることを忘れるな
12 夏のスンガリーでの遊び――大幅な加筆
13 ことばの「ありがたさ」と「おそろしさ」――「悪いことば」の追求
14 仲間はずし
15 仲直り
16 がまんくらべ――言ったことは守る
17 一家で中国大陸へ写真報国に
18 付録 加藤武雄『饒河の少年隊』
第Ⅳ部 戦後の石森児童文学における満洲
1 石森の戦後満洲児童文学三部作
2 『わかれ道』――日本喪失から満洲追憶を経て「故郷・新生日本」へ
3 『秋の日』――孤独な少女の満洲懐旧
4 『親子牛』――親しい中国農民をつてに故郷・満洲で営農の再出発を夢みる
(1)この作品の独自性
(2)『親子牛』の登場人物
(3)開拓村の生活
(4)キリスト教やイスラエルとのかかわり
(5)酪農開拓地リーダーの死
(6)ケンの希望とチンさんからの手紙
(7)「農」に根ざすということ
5 懐かしの満洲――戦後三部作の主人公の心情
6 参考『ふしぎなカーニバル』と『太郎』――満洲帰還者による救済
第Ⅴ部 満洲児童文学の背景としての在満日本人の生活と教育
1 在満日本人の実態――永住の地ではない満洲
2 在満日本人教育における「現地適応主義」と「内地延長主義」
3 『満洲補充読本』の内容と性格
4 石森の『満洲補充読本』編纂への参加と満洲児童文学の誕生
5 『満洲補充読本』の改訂と満洲郷土論
6 石森延男の満洲児童文学と自然美中心の満洲郷土論
7 観念としての満洲郷土論
8 大連は「満洲の日本」か
おわりに
参考文献
著者プロフィール
磯田一雄(いそだ かずお)
1932年東京都生まれ。
成城大学名誉教授。
東京大学大学院学校教育学博士課程満期退学。
専攻:教育方法論、植民地教育文化史。
主な著書:『授業の原理を求めて――主体的な教師になるために』(教育出版)、『子どもたちのマジソン――アメリカの学校生活体験記』(教育出版)、『「皇国の姿」を追って――教科書に見る植民地教育文化史』(皓星社)、編著『日本の教育課題 9 教師と子どもとのかかわり』(東京法令)、共編著『在満日本人用教科書集成』全10巻(柏書房)。
主な論文:「野村芳兵衛の生活教育思想」『教育学研究』34巻1号、
「戦後台湾俳句小史(一)~(七)」『成城文藝』239号~245号、他多数。